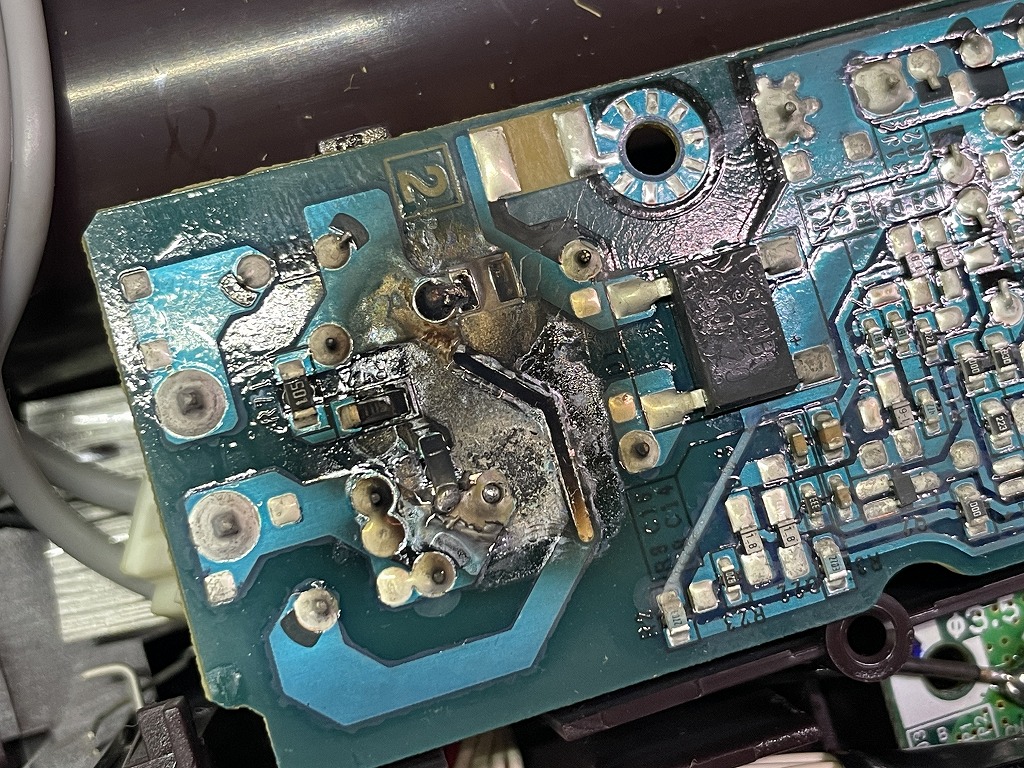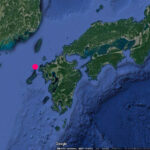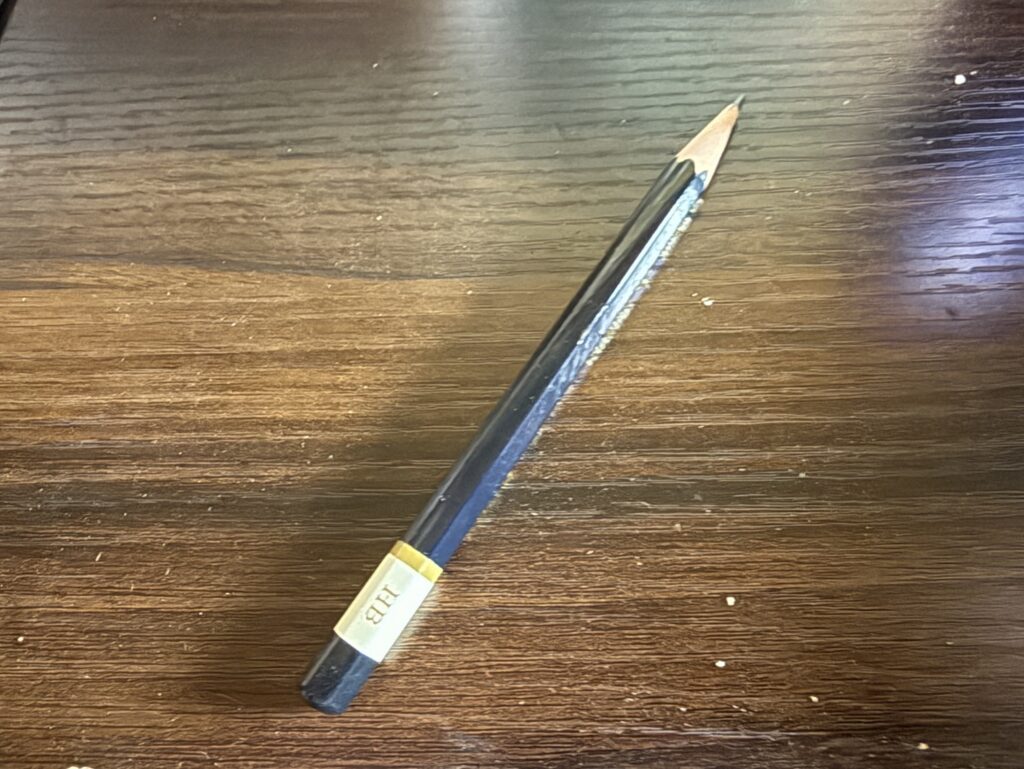しきりに人手不足を嘆いている本ブログですが、凄く小さな島の現状=リアルについて参考になっていれば幸いです。
コロナ明けから露骨に人手不足を実感してきました。
猫の手も借りたい、とは言ったもので人間だったら誰でも良いや、みたいな風潮になっている気がしますw
そもそも、昔から絶対におかしい、と思う出来事があります。
地域おこし協力隊の存在。
自分も移住当初は地域おこし協力隊とよく間違われていたのですが、当時はそもそもそんな存在は不明でした。制度自体あって、それを活用して移住してきた人もいました。
ただ、総務省の言うそれは、地域(地方)に移住者を増やして、活性の起爆剤にしたいという願いから生まれたもので、主に成功した例に共通することは自主性を持って活動していた人たちと、それをバックアップしてあげられる環境が整っていたことに尽きます。
逆に失敗する例としては、制度上3年後には協力隊(隊員)の任務を解かれ、自分でその地で就職するか起業するか、地元に帰るか選ばないといけないのですが、その3年後の目標設計ができていない人。
酷ですが、協力隊員全員に言えることで、3年後は国は面倒見てくれません。自分でなんとかしてね、ってスタイル。まぁそれでもありがたいことだと思いますけど。
なので、なんとなく来た、とか頼まれて来たとか、中途半端な理由で来た人は事例を見る限りどこの地域でも失敗してます。
それくらい地域おこし協力隊になる人はビジョン持って応募していただきたい。偉そうに申し訳ないですが、その地域の人たちが迷惑するから。一応地域おこし協力隊と聞いて、地元の人は何らかの期待を持ってその人に接します。それが期待外れに終わったら手のひら返してきます。地元の人の期待も大から小まで千差満別。それらを解決することって協力隊が活躍することしかないんです。
そして、逆に応募している自治体に対して。
何を持って募集かけているのでしょうか。
ターゲットを定めているのでしょうか。その地域に足りないものを補完するため、よりよい地域にする為に募集かけるのではないのでしょうか。成功している自治体はそのターゲットについて具体的に明示することで適材者を獲得しています。
釣りで観光振興したい、という自治体が「釣りと観光を結び付け、地域の人を巻き込んだ町おこしをしたい人募集します」と書けば、釣りをしない人は来なくて釣りが大好きなやる気ある人が集まってこないですか?「地域おこし協力隊募集します。地域を起こしたい人来てください」じゃ、まるっきり何をすれば良いか、どこに向かってベクトル合わせれば良いかわからない。
そしてなんとか採用した人が何をしてよいかわからない状況を見て「こんなはずじゃなかった」と匙を投げる。
もう少し議論を詰めて欲しい。書いててイライラしてきたw
その地域を好きになるには時間がかかる。好きになるために協力隊に魅力を感じた人は努力をする。雇った側は責任を持つ。当たり前の仕事のあり方だと思います。
誰でも良い、のスタンスはその地域の不和すら生みかねないです。
※その地域=自分の島の事です。本当にダメになる前にみんなで環境変えていきましょう!